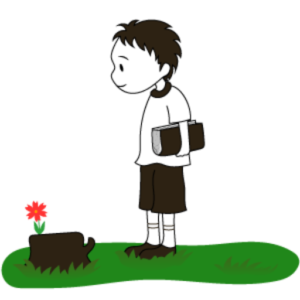急に寒くなった。
こんなに急激だと、身体が付いていかない。
普段、スポーツ中継以外には、テレビはめったに見ないのだが、たまたま付けたとき、新たに始まった戦争関連のニュースをやっていた。
「平和」、「少しでも早く訪れて欲しい平和」、「平和の希求」。司会者を始めコメンテーター全員が異口同音に同じ事を言っていた。
しかし、そんなことは誰でもわかっていることでもある。平和が素晴らしいことを。命が暴力で奪われることがひどいことも。
平和の姿というのは、天国や極楽と聞いて思い浮かべるように、人はだいたい同じイメージを浮かべることだろう。しかし、実はそこに落とし穴がある気がする。
かつて芥川龍之介が、「もし、みんなが思うような天国あるとしたら、ぼくは三日で飽きるだろう」という意味のことを言っていたが、平和も同じで、実はこのぼんやりした平和のイメージこそが、戦争を生みだしてるかもしれないのだ。
表向きは、このクラスは、みんな仲良しと言いながらも、裏では陰鬱ないじめが存在したり、舞台上では夢うつつの華やかなレビューが演じられながらも、凄惨なパワハラがあったりと、表向きの平和、理想郷の希求こそが、返って戦争を生み出す源となり、戦争は「平和」だからこそ存在しているかもしれない。
平和について、多くの人は同じような意見を述べるが、戦争自体について考える人が少ない気がする。
ただ「悪いこと」の一言で片付けられてしまう。
もちろん「いい戦争」などこの世にはないけれど、人が人である限り、これからも戦争が起こりえるなら、戦争自体についてもっと考えてもいいのではないかと思う時がある。
「人々が殺し合うこと」それは、必然なのか偶然なのか、抵抗なのか抑圧なのか、国権の発動なのか軍部の独走なのか、侵略なのか集団的自衛権なのか、まだましな方の戦いなのか、極めて卑劣な方の戦いなのか。
だから、マスコミも真実を知らせるために、敢えて、マジックワードである「平和」とか「戦争」という言葉を、安易に使わない方がいいような気がする。
「戦争を学ぶ」、それを口にすると、どこか反道徳的で、ただ平和を愛する人から怒られるかもしれないが、ふと目をそらしたくなるそんな残虐な行為の中にこそ、逆に本当の「平和」を知る手立てがありそうだ。
改めて言うことではないけれど、この世界は戦争の歴史とも言ってもいい。
「平和とは、戦争と戦争の間の休憩時間をさす言葉に過ぎず、それが長いか短いかはただの運」と、どこかの思想家が言っていたが、言い得て妙だと思う。
と、一分ほど見てスイッチを切ったニュース番組を見ながら、いい具合に熟れた柿をむいて食べる。
たとえ、どんな戦いの最中にあっても、生きるに値する美を見出すべく、今日もまたヘボ俳句をひねる。
“うまき柿 戦い願う 者はなし“