読み終えて、一ヶ月ほどたちました。
すぐに、感想を書こうと思いましたが、なかなか筆が進みませんでした。真剣に書こうと思えば思うほど、手が止まり考え込んでしまう。
その間にもNote上には、感想や批評の記事が次々に上がっていく。
それらを読みながら、時にはなるほどと思うし、的外れだなと思うときもありました。当然、本の読み方に正解などありません。
批評というのは、まったくの的外れでもいいやぐらいに思っていますが、ただ間違ったまま、こき下ろして終わっているの読むと、さすがにもやもやした気持ちにはなります。
といったわけで、おそるおそる感想を言わせてもらうと、別に奇をてらって言うわけではありませんが、この作品は、村上春樹さん(以下敬称略)の、最高にして最低な傑作(けなしているわけではありません)だと思いました。
みなさんが書かれてあるように、この作品は世界の終わりとハードボイルドワンダーランドの世界観の継承し、そこにノルウェーの森、騎士団長殺し、など、これまでの村上春樹の小説のエッセンスを絶妙に取り込んでいます。村上春樹の集大成と言っても良いでしょう。
それとは別に、私が最高傑作とだと言うのは、ノルウェーの森の中では果たせなかった、失われた愛の再生と完成を見事に描ききっているからです。
ノルウェーの森では、直子が自殺し、救いきれなかった主人公は、現実的な魅力を備えた緑に惹かれ、彼女を選んで終わる。とても悲しいけれど、リアルな終わり方だったと思います。
しかし、この小説では、結局「緑」では満足できなかった、できないという事実の後日譚だと思います。
主人公は、自我でさえ捨ててしまって、失われた愛を取り戻そうとした。騎士団長にも出てきたイデアの力を借りて。
その後日譚の物語は、村上春樹という小説家というより個人でしか書けない、唯一無二のオリジナルなもののような気がします。
この作品、一見するとファンタジーっぽいですが、実は、改めて言うのも恥ずかしいですが、究極の純愛(書きながらぞわっとしましたが)が描かれています。
そういう意味で傑作であり、つまり、村上春樹が一生の間に願った「失われた愛の再生と完成」の物語。
大げさでも何でもなくノーベル文学賞にも値する作品だと思います。
実は我々も、現実の中で失われ、決して蘇らない愛の補完の仕方をそれぞれの方法でやっています。天国で再会するというベタなものから、生まれ変わって再会するというものまで。何とかして失われた愛を再生しようと、一つの物語を作り上げます。
この小説の主人公のように、己(意識)を崩壊させてまで、失われた相手の意識の中を追い、ついには一体化させてしまうというのも、その一つでしょう。
主人公は、現実と夢の世界が混じり合うイデアの中で、最後に究極の愛を完成させる。それは形而上学上の「心中」と言い換えてもいいのかもしれません。
しかし、それがよりパーソナルなやり方であればあるほど、人の共感を得ずらくなります。その証拠に、多くの人はあの壁の中の街に住みたいとは思わない気がします。
しかし、小説の中の主人公はあの世界の中でしか、己の失われた愛は完成できなかった。事実そうだった。
この作品は、ひとりの作家がしかるべき時が来て、絶対に書くべきテーマがあるように、これは村上春樹という作家のメルクマールであり、己の救いを描いた物語とも言えるでしょう。
同時に、最低だったという意味は、それが傑作であってもノルウェーの森を読んだときのような、感情の震えが一切起きなかったことです。読みながら、すごいなあ、深いなあと思いながら、同時にずっと覚めたまま自分がいました。
自分が好きな長編小説は、とにかく感情が震えたか震えないかだけです。
(あくまで私流)。
音楽で言えばロマン派の交響曲、小説で言えば、スタンダール、ディケンズのような作品です。
べつに文体そのものに美学やきらめきや斬新さなどなくていい。物語の中に矛盾があろうと、伏線も回収されずに言いっぱなしであろうと、論理的に破綻していようと、結果的に心を震わせてくれればいい。
一言で言えば「芸術は爆発だ」です。
それが音楽でも絵画でも、たとえ文学であっても。芸術に求める基本的なスタンスです。
「爆発」、ともかく言葉がもたらす強烈な爆風で、私の心をどこか遠くに吹き飛ばしてばしい。宇宙の果ての果てまで、とつい期待してしまうのです。
そういう意味で、「最低」と言わせてもらいました。最高にして最低傑作。あえてそう言ったのは、村上春樹作品をずっと好きで読んできたからこそ。
そしてもう一つ、これは感傷にすぎませんが、主人公はノルウェーの森の主人公のように、現実世界にいる女性、緑のような女性の元に帰って行く(と思われる)。
このように第三部は終わるのですが、自分は最後の二行がとても気になりました。これだけ読むと、主人公は本当に彼女の元に帰って行けたのかどうかわかりません。
たしか、イエローサブマリンの少年は、目の前のろうそくを消せば、すぐにでも現実の世界に移ってしまっているというが、この二行はただの暗黒としか書かれていません。
思わず、ノルウェーの森の中エンディングで、電話ボックの中で主人公が緑と電話しながら、今居る場所がわからなくなり、景色が見えなくなくなっていくシーンを自分自身でオマージュしたのかもしれません。
しかし、その意味は決定的に違っています。ノルウェーの森は現実世界には緑がいる。それでエンデヒングだったと思います。
ノルウェーの森が書かれて三十年ほどたち、緑が、いくら現実の世界で魅力的であっても、「主人公にとって、結局のところ緑ではダメであり、直子しかだめだった」という残酷な真実。
それがわかってしまった人は悲劇です。たとえイデアの中であっても、心中が達成すれば、現実に残った私は暗黒の中に消えていくしかない。
それは、村上春樹という作家が抱き続け、ずっと描き続けてきた地獄でもある気がします(違っていたらすみません)。夏目漱石が三角関係をずっと描き続けたように。
だからこそ、この作品はあまりにも村上春樹の個人的物語過ぎて共感しずらく、同時に井戸の下に潜りすぎてある地表に達した。最高にして最低。それが評価がわかれる所以だと思います。
もう一度この作品を、頭から読み返したいですか?
それが答えのような気がします。
ではまた
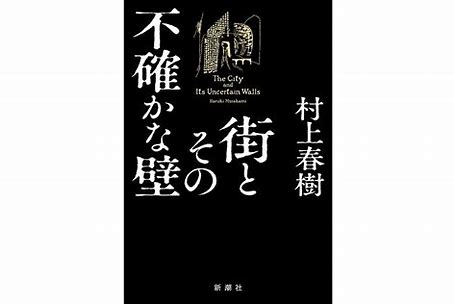
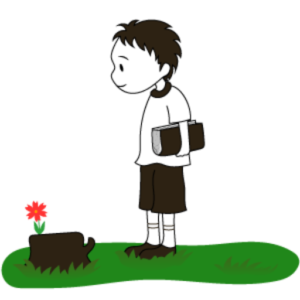
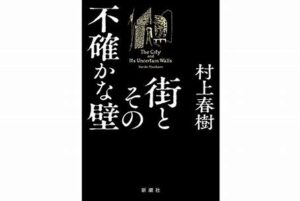
-192x300.png)








