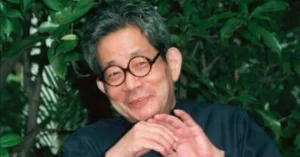久しぶりに講談社の児童文学新人賞を調べようと、講談社のホームページに入る。
何か様子が違う。
賞自体がコクリコというWEB雑誌の中に吸収されてしまっていた。
さらには、このWEBの中には絵本や童話が溢れていたが、物語分野が皆無に近い・・・悲しい。
それに昨年には、長年、児童文学の大切さを訴えていた故河合隼雄さんがやられていた児童文学ファンタジー大賞も募集停止になり、なり手の登竜門も年々少なくなるばかり。
昔は、青い鳥文庫という、一大勢力が本屋や図書館の棚一角を占拠していたが、今は見る影もない。絵本コーナーのふちのふちに追いやられてしまっている。このWEB雑誌にも、その事実が如実に反映しているのかもしれない。
小説も読まれないのに、児童文学が読まれるわけがない。当たり前といえば当たり前か。
そう言って落胆していても仕方がない。できることしかできない。要するにいい作品を創るしかない。結局はそれに尽きてしまう。
ただ、肝心のいい作品とは何ぞや。それが難しい。どういった話が子供たちに喜ばれるのか、それは大人側からするとほぼ未知の分野だからだ。あのアンパンマンも、最初は大人には理解されずに、子供たちに見いだされて売れ出したという。
きっと、子供達には独自の面白センサーのようなものがあるのだろう。そして、多くの子供達が突然アンパンマンを飽きてしまうように、突然センサーが切り替わってしまう。いきなり残虐な漫画を読み出す。そのスイッチの仕組みもよくわからない。
だから、いい作品とは子供のセンサーに引っかかり、そしてセンサーが切り替わっても読まれ続けられ、さらには大人になっても何度も読み返してもらえる作品なのだろう。自分も、時々ムーミンシリーズや、星の王子さまを読み返すように。
先日、児童文学をやり始めた初期の作品を電子化して発表したが、一人の創作者としては、小さな子供から、大人まで何度も読んでもらえる作品になっていってもらいたいという親心だけだ。
児童文学っていう言い方に少し違和感があると、以前の記事に書いた気がするけれど、子供には無限の可能性があるように、児童文学にも同じぐらいの可能性が秘められていると思う。
たまに、子供向け文学全集と銘打って、夏目漱石の「こころ」や、芥川龍之介の「杜子春」とかがよく入っているけれど(あと、江戸川乱歩)、それらは名作だけれど、正直言って小学生などの子供が読むにはちょっと早い気がする。
代わりに何がいいと言われれば、「モモ」とか、「アルケミスト」とか、「ゲド戦記」とか外国の作品が上がってくるのだろうけれど、日本の作品が中々挙げられない(クレヨン王国は好き)。
だからこそ、大人は「こころ」を入れたくなるのだろうけど・・・やっぱり違う。
絵本の世界に、突然ヨシタケシンスケさんという傑物が現れて、絵本ブームが来たように、誰か出てこないかな。児童文学の世界を一緒に盛り上げて行けるような人が。
と、自分の作品力を棚に上げて、勝手に児童文学の将来を憂う仲村でした。
ではまた

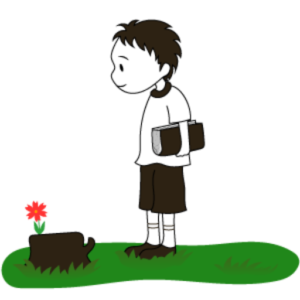

-188x300.png)