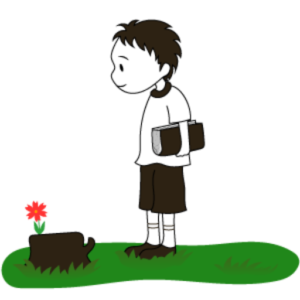久しぶりに雨
体調が復活気味
毎日noteを書いていると、突然何も書くことがないと思う日がどうしても出てくる。けれど、政治、経済、ワールドカップなど、少し眼を凝らせば、それらしい話題には事欠かない。
だから、書こうと思えば書けなくはない。しかし、そう思ってもどうしても書きたくない。興味がないことを無理矢理書こうとすると、どうしても評論チックになってしまう。評論を書くのは、割に楽だ。対象を批評すれば基本的に成立する。
それは、多くのヤフコメを見ていればよくわかる。そして、つい癖になりやすい。必ず文章が荒れてくる。
小林秀雄や吉本隆明といった一流の評論家となれば、評論も一つの文芸になりえるが、そこまで達するには、深い洞察と知識、批評眼が必要である。
私には、そんな凄い眼を持ち合わせていないので、どうしても、評論を書くと、浅い考察になってしまう。おまけに、対象に興味がないから、文章に血や肉が宿っていない。結果として書いていてつまらない。歯が浮いたような文章になってしまう。
まあ、それは、それでいいのかもしれないけれど、やはり小説家の端くれとしては、遠藤周作の狐狸庵シリーズのように、一見軽い文章に見えたとしても、そこには一つの「念のようなもの」がこもってないといけない気がする。そして、その「念のようなもの」の有無が、一流の文章と駄文を分ける境目に思える。
昔から、小説家が評論家(批評家)を嫌うのは、その「念」というものをつくるのが創作者にとっていかに大変で、すさまじい体力と、精神の消耗を伴うことを安易に考えすぎている気がするからだと思う。
あのドラゴンボールの悟空が「かめはめ波」を習得して、使いこなすまでが実は結構大変だったように(たとえがくだらなくてすみません、つい「念」というと)小林秀雄や吉本隆明は、もともとは小説や詩を書いていた(ちなみに小林秀雄の処女作は『蛸の自殺』、親友の中原中也から、みじめな自意識がぽやぽやと浮いているだけ代物と、酷評されたらしい)。
その創作者の「念のようなもの」をこねることの大変さをよくわかっていたからこそ、一流の評論家になれたのだと思う。
しかし、そうした「念のようなもの」は、頭で考えて出てくるものなのか、厳しい人生経験から生まれてくるものか、そもそも生み出す必要があるのか、ないのか。書きたいことがたくさんあるけれど、どうしても書けないときに、ふと考えてしまう。
まあ、そもそも、それほど読まれるわけでもないんだから、無理して書かなくいいんじゃないと言われれば、それまでだけど。
耳すまし 心静まる 小夜時雨