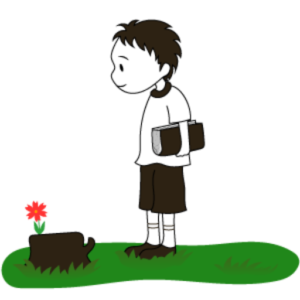晴れ
11月11日 何となく語呂がいい。良いことありそう・・・でもなかった。
今、一番行きたいところ。それは、早稲田大学の国際文学館(村上春樹ライブラリー)。
当館は、文学資料館であり、また文化交流施設です。
「村上春樹ライブラリー」の通称に示されるように、刊行された村上春樹作品を―日本語・日本語以外のものをあわせて―所蔵しています。関連書とあわせて、ギャラリーなど閲覧スペースでご覧いただける蔵書が3000冊(2021年10月現在。以下も同)あります。
刊行書でも初版本など貴重なものに加えて、村上氏からの寄託・寄贈を受け、研究書庫には、執筆関係資料、インタビュー記事・作品の書評、海外で翻訳された書籍(50言語以上)、さらに村上氏が蒐集したレコード・CDを中心に収集しています。
資料の収集・整理を、開館後も継続し、適宜研究者の閲覧に供するようにします。これが、「村上春樹文学」「国際文学」「翻訳文学」の研究の進展や、新しい表現活動の展開に寄与するようにします。
国際文学館 HPより
さらに、ミッションとして
ミッションとして、誰もが集う「文学の家」を皆さまと創造するための施設です。
国際文学館 HPより
このミッション、すばらしい。
しかし、今は、名古屋に住んでいるので、中々行けない。
どうして、素晴らしいのか。たぶん、「文学の家」というコンセプトがいいのだと思う。
世の中には、作家の記念館はたくさんあるが、そのほとんどが箱物で、時の流れともに古びて消えていく、文学の世界での箱物行政みたいになっている。
しかし、春樹さんの場合、母校の中に作り、「文学の家」として、交流の場として提供するのは、作家の記念館(じゃなかったごめんなさい)として、とても斬新に思えた。
もし、自分が一流の作家で、死んだ後に記念館ができたはいいものの、その何十年後、建物が古くなり、改築もされず、訪れる者もほとんどなくなり、からーんとして、地域のお荷物のようになっているのをあの世から見たら、「あーあ」と、思わずため息をつきたくなるだろう。
事実、若山牧水、尾崎放哉、等、これまで好きな作家の記念館をあれこれと巡ったが、賑わっているのをほとんど見たことがない(司馬遼太郎さんが一番賑わっていたかも)。
しかし、キャンパスそのものをミュージアム化する目標を抱く早稲田大学の中に作ることで、まるでディズニーランドのいちアトラクションとして、常に更新され続ける、理想の記念館になり得る。
それは、文学に携わった者の、そして文学の魅力に取り憑かれて、少しでも文学の世界に触れて欲しいと願う者にとっては、この「文学の家」のあり方は、新しい可能性のような気がする。同時に、これからの大学と文学の関わり方においても。
と、少し真面目に書いてしまったが、絵を始めとして、小説家、陶芸家、などのクリエーターが、形ある「場」を残すというのは、ひょっとして、「作品」を残すことと、根本的に相容れないことかもしれない。
「作品」というのは、時の流れに翻弄され、浮かび流れ、より多くの人の手の中に渡っていき、ただ受け手の意識の中だけに残っていくべきもののような気がすることもある。いったい、どっちなんだろう。
紅葉し 枯れ木も生まれ 秋深し