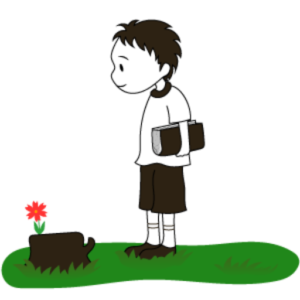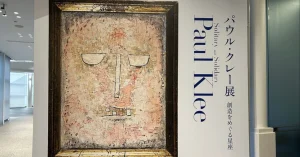「自由」という言葉。
おそらく嫌いな人はいないだろう。自分だって大好き。
自由についての本というと、まず最初にイギリスの哲学者ジョン・スチュアート・ミルの『自由論』や、 エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』が思いつく。
そういった本を読みながら、自分もそれなりに「自由」について考えてきたし、読書も重ねてきたが、今でも頭に残っているのは、前掲の2作ではなく、故池田晶子さんが書かれた「自由」に関する考察と、あとは小林秀雄さんが書いた「自由」についての断片だろう。
まずは池田晶子さんが主張する「自由」とは、人というのはもともと「自由」を持っていて、日常の不満程度の範囲で使っているだけであり、不自由と思っているのはその人の自身の思いでしかないということ。
ただ、自分が自分を不自由にしているに過ぎない。
つまり、人は自由に「思う」ことができ「行動」ができ、その思考の結果が今の人生に過ぎない。すべては自由に選んできた結果なのだ。
生きる死ぬの選択を含めて、人がかつて自由でなかったことはない。ただ世間体や常識、そしてお金の不安に縛られて選べないだけであり、それはただの人生の覚悟の差でしかない。
というか、そもそも自由を本当に得たいと思っていないから。
ぼわーんと「自由」という語感に憧れているだけだと言い切る・・・ある意味手厳しい。
たしかに自由の本質を考えずに、ほとんどの人は、自由の反対である不自由ばかり嘆いて「我慢」を不自由の意味とはき違えている。
そう「自由」はすでに、あなたの自身の手の中にある。メーテルリンクの青い鳥のように、決して自分の外にあるものではない。自分も彼女が言うとおりだと思う。
一方で小林秀雄が言う「自由」はもう少し現実的だ。
ご存じのとおり、小林秀雄は戦後の偉大な文芸評論家であり、戦前に生まれて、第二次大戦を経て戦後まで生きておられた。
とくに青年期には、ひたひたと軍国主義の雰囲気が忍び寄る時代。検閲も日に日に厳しくなり。役に立たないと思われていた文芸家すらにも、戦争報道記者など現実的な国家貢献が求められはじめたご時世だった。
もちろん、小林秀雄は文芸の人であり、当然ながら戦争は嫌い(本質的に)。人間の営みの中で最大級の「悪」だとわかっていた。
そして、こうした戦争に対して、反対するのも文芸家の使命だとは思ってはいたが、現実的なイデオロギーを持って国家権力と闘った林房雄や、埴谷雄高や、拷問死した小林多喜二とは違い真っ向からは闘わなかった(中原中也からは戦争すら利用する文芸家と罵倒されたらしいけど)。
彼は政治を含めて、イデオロギーで世の中を変えようとする行為そのものを嫌っていた。だから歴史や世相の大きな流れはどうしようもないと受け止めて、激しい葛藤を抱きながらも、その中で自分ができる範囲での身の処し方を考えていた。
うねりに似た戦争への流れは、どうしても個人としては抵抗しようがない。いくらデモをしようと、選挙に行こうとも。食えない文士などさらにそうだ。その時代に生まれて生きるしかない。それは、毒親の元や、障害をもって生まれたのと似たようなところがる。
まさに時の運である。
かといって、ただ黙って戦争に突き進む世の中に対して、あっさり白旗を揚げるのも「悪」である。
逃れらない時代や環境に対して、自分ができる範囲の中で、最善の選択肢を考えて選ぶということ。それが人間の唯一持てる「自由」の意味だと。
つまり小林秀雄のが言う「自由」とは、限定的なものに過ぎない。
言い換えると、もし右手が不自由になったとすると、右手が動かないことを嘆くのではなく、左手でできること、普通の人の左手以上でさまざまなことができるようになる。なんとか生きるための工夫する。それが、人ができる唯一の「自由」の意味なのだと。
だからこそ、「自由」には価値がある。そんなことをおっしゃっていた(違っていたらすみません)。
おそらく、これを死に言い換えるともっとわかりやすいかもしれない。自分に放たれた矢が、額に刺さる二秒前に気づいたとしても、それはもう、もはや逃げることができない。だったら、その二秒の間で何ができるのか。
なんとか、少しでもよける努力をするのか。あきらめて神の名前を叫ぶのか、過去の行為を懺悔するのか。
しかし、矢はもうすぐ目の前に迫り、気がつけばあと一秒で突き刺さるのがわかっている、その中で選べる選択肢が多いほど、そしてより「善」を選ぶこと、それが「自由」だと。
だから、何の束縛もなく、己の欲望に身を委ねて、好き勝手やることが自由とは決して言わない。自由業が自由というわけでもない、サラリーマンだから不自由でもない。
それはただの感覚の上での自由に過ぎない。そこは、池田さんと似ているかもしれない。
つまり、自由とは考えに考えて、己の意思で勝ち取るもの。人は生まれたら必ず死ぬ。死なない人はいない。その限りにおいて人ができる選択。それこそ、人の数だけある。
それがつまるところの個性であり多様性なのだ。
そういう意味で、自由を考えるのはとても大切なことであり、もし自由を欲するなら常に勝ち取らないといけないものだ。
まあ、どうせ額に弓矢が刺さるなら、それまでは娯楽、快楽三昧に浸って待つというのも、ひとつの考え方ではあるけれど。
実際の問題はいつその矢が己の額を打ち抜くか、誰もわからないということ。そして、死の二秒前、人ははたして自由を感じられるのか。今が自由と思えるのか、それが自由という言葉を最大限に大事にする人の、本当の意味の勝負のような気がする。
〝どうしてか こうしてかと という人生を こうであったとは 言い切れぬなり 〟