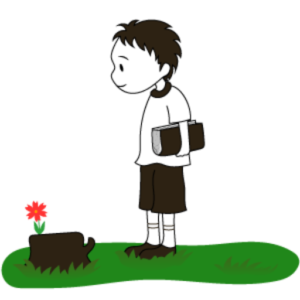とうに死語である三文文士とうそぶいてみても、しょせんは売れない一介のクリエーター。
専業で食べては行かれてないし、作家として定期的な収入があるわけでもない。
噂によると、SF・児童文学・ライトノベル分野を含めて、専業の小説家として食べているのは、わずか50人足らずという。
おそらく職業小説家として一生を無事終えられる数は、もっと少なくなるだろう。
今の時代、たとえ有名な賞をとっても、書き続けたいなら兼業ありき、副業ありきなのは大前提で、受賞後に編集者から最初に掛けられる言葉は、「仕事(本業)は絶対に辞めるな」らしい。
かつては、小説家という職業も、消防士や警察官とまでは言わないが、れっきとした職業の一つだと社会的に認知されていた。当然、子供がなりたい職業の一つにも挙げられていた。
「いつかは作家になる」。
それは、今のような兼業ありきではなく、れっきとした専業のことを意味した。赤川次郎、吉本ばなななど、かつて新聞発表にのっていた高額納税者一覧にも小説家部門というものがちゃんと存在していた。
しかし、時は流れてこの世は出版不況。
本屋はなくなり、本自体が売れなくなるどころか、本を読む人自体が少なくなってきた。
それは、日本だけではなく世界的な潮流でもあるらしい。
しかし、たとえ世間知らずで、将来の見通しがなかったにしろ、大きくなったら小説家になろうと夢見て、一生の職業にしたいと志した人は、この今の状況を見て、いくら頭では理解していても、
「嘘だあ」、「そんなの詐欺じゃん」という感情を抱く者も少なからずいるとは思う(少なくとも自分は)。
昔話になるけれど、かつの文芸雑誌や、若者のファッション雑誌が売れていた頃、有名人気作家の趣味の話や、派手な交友、豪勢に世界を旅したり、おいしいものを食べ歩いたり、映画を撮ったりしている華やかな生活の記事がよく載っていた。
まだ子供だった自分は、そうしたライフスタイルに憧れて、小説家になって成功すれば、こうしたことを自由に満喫できるんだなあと、単純に思い込んだ。
しかし、今はその雑誌自体売れていないし、華麗なる作家生活の記事なんて、ネットニュースを含めても皆無である。あるのは苦労話と人生相談ばかり。
もちろん、世界の文学史に名を残したい、永遠に作品を創るという崇高な目的を掲げて文学をやりはじめた人もいるとは思う(これもとても大事なことだけど)、そういうだって、こうした小説家の成功者エピソードにあこがれ、夢見たことは絶対に一瞬はあると思う。
もちろん、職業作家が絶滅したのではなく、少なくなっただけでちゃんと食えている人が存在する以上は、
「もっと努力して頑張って、売れるものを書けばいいじゃん」と言われたらそれまでだが、どうしてもどこか華やかな世界へのはしごを、突然外されたような気がするのは否めない。
それは、まさに二十歳のときに、この先40年間きちんと年金を払えば、60歳から充分生活できるような年金がもらえると言われていたのに、いざ令和に入ると65歳支給開始となり、そのうち70歳の可能性もあると言われ始めている。そんな状況へのがっかり感、しょんぼり感とどこか似ている。
もちろん、出版業界の衰退は国のせいではないし、そもそも国だって衰退家電業界以上に出版業界には何もできないし、手も打てない。
いくら、本をもっと読みましょうと声高に叫んでみても、読まない人は本を読まない。
だったら電子書籍ならどうか? いくら普及しても、ライバルはスマホ上に同じように並ぶ、ゲームや動画アプリとなる。競争は厳しい。
ゲーテが(ちなみに鈴木結生著の「ゲーテは全てを言った」はすごい)と言っていたように、文芸が衰退する文明は滅ぶと言っていたが、この論法で言えば、人類の文明自体が滅びつつあるのかもしれない。
と、世界的潮流にいくら文句を言ってもしょうがないが、とにかくいい作品を書いていこうと決意しながらも、同時の頭の片隅では、初版の出版部数はこうだから印税はこうで、重版だといくらで、この先年間何作書けて、収入はこうなると、自然にシュミレートしてしまう自分がいる。
こうしてみると、小説を書く行為ということは、今流行の「タイパ」や「コスパ」(本当に嫌な言葉)という観点から言えば、かなりの劣勢な分野でもある。まあ、この言葉が意味するのと真逆の行為だからこそ文学はいいんだけど。
そうなると、話は元にもどって、作家としてやっていきたいなら、どうしても兼業ありき、副業ありきの話になる。
それはつまり、文芸などは趣味や余芸に近くなるという意味でもある。そうなると、命をかけてまで目指す人も少なくなるし、小説の質が落ちていくのも自明なことである。
だって、食えないんだもん。その言葉が意味するところは強い。
ただ、小説を書くのは楽しい行為である。そんな文学史に名を残すといった大きな望みを持たなくても、最初から副業、趣味と割り切れれば、それはそれなりにお勧めしたい趣味にはなるとは思う。
けれど、そこから生まれた作品が、歴史に残るような作品になるかと言われると、たいそう怪しい。隠遁者の余技から生まれたような徒然草や方丈記などの作品は、まさに僥倖と言ってもいいだろう。
結局は、悪貨は良貨を駆逐するのことわざ通りを証明していくのかもしれない。そして、文芸はいつしかオール趣味のものとなり、読む人より書く人の方が多くなっていく。
だったら、この状況をどうすれば、いいのか? とりあえず文学賞を10分の1にするのはどうだろう。
全国の県や市町ごとにある、町おこし的な賞をとりあえず減らしていく。芥川賞も全出版社共催の新人賞として一年に一度とする。
本屋大賞や、大きな賞はベテランに与える一つの賞に統合して、そのかわり最大級の名誉と、高額賞金を設定したらどうだろうか。テレビなどで大々的に授賞式を行う。
アメリカのピューリッツァー賞のように。
お笑い界でもM1グランプリがブランド化したように、高額賞金で潤うとともに、成功の足かがりとして定着するかもしれない。
本当に素晴らしい作品を作った者は、ありあまるお金と名誉でも報われる。そうしたシステムがあればいいなあと、個人的には思う。
それって、あんたのようなニッチな児童文学を書くような人は、もっと状況が辛くなるじゃない?と言われると、それまでだけど・・・
“ 文学賞 もっと銭くれ 名誉くれ ”