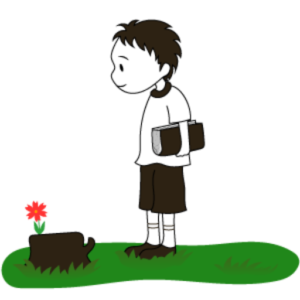文章には正解がない。
散文だと、よけいにそうかもしれない。
これまで何回も読み返している、萩原朔太郎の「詩と原理」によると、
詩は音楽に似て主観的なもの、散文(小説)は絵画に似て客観的なもの。
とある。
ただし、どの文章もどちらかにきちんと分けられるものではなく、どちらか寄りになる。
自分は死ぬほど小説を書いておきながら、それほど文章が上手くないと思っている。自己評価、中の下ぐらいのところかな。
もし、上のレベルだったら、とっくにベストセラー作家になっていたことだろう。
若い頃、それはただ努力、修練が足りないからだと思っていた。絵画で喩えるなら、デッサンから始まって、構図、色合いなどなど、きちんと勉強をする必要があると。
そのため、三島由紀夫に、谷崎潤一郎、高橋源一郎さんなど、この世に溢れる数々の小説技法を読んで、実践してきたが、一向に上手くなる気配がない。
と、その後あるとき気づいた。そう、自分は小説の勉強などしたくないということが。
まるで建設する家の設計図を書くように、あらかじめテーマを定め、おおまかなストーリーを決め、そこにエピソードを散りばめ、伏線をいくつも張り、その回収と、最終的な結末を考える。
それは、多くの創作教室でも教えていることでもある。
しかし、自分にはその作業がとにかく嫌なのだ。もちろん何の目的もなく、文章を書く脆さはわかっているので、ある程度の目安は決めるけれど、細かい設定や、登場人物を考えようとしたところで、手が止まる。
もちろん、こういうやり方が合っている人もいるだろうが、自分は致命的にだめだ。書いていてどうにもつまらない。ぼやっとした家が建つだけだ。
ただ、音楽のようにピアノの鍵盤を無造作に叩きながら、メロディーを奏でていくような書き方が好きだ。これは、もうどうしようもない。
こんな書き方で、完成度が落ちるのはわかっているが、没我のような気持ちでタイピングしていくのが最高に気持ちがいいのだ。
それは、どこか絶叫するパンクロッカーの心境に近いかも知れない。
最後は、小説を書くとは何ぞやという難しい問題に行き着いてしまうが、やはり自分は、「ただ思いを言葉にしていく」そこに、幸福を感じる人間だということだ。
勝手なイメージだが、自分はベートーヴェンよりも、モーツアルトが好きだ。文豪というよりも、即興詩人の方が好きだ。
だから、毎日自然に、一枚はなにがしらを書いている。ほっといても書いている。というより書かないと、自分の意識が曇ってしまう。いつのまにか、淀んだ不快な気持ちに支配される。
きっと、一流の小説家はこんな書き方はしないのだろう。するとしても、後で、平野啓一郎さんや、村上春樹さんのように、ねっちりと推敲、校正を重ねるに違いない。
次から次へと「書き殴る」それこそが、最高だと思うような人の作品は、果たして芸術と呼べるものになりえるのか、人に読んでもらう価値になり得るのだろうか。と時々考えこんでしまう。
ただし、どんな文章になろうと、詩だろうと、長編だろうが、短編だろうともどんな作品になろうとも、出来上がった自分の作品を見て、「やさしい詩になったな」といった感想を持てれば、大成功としている。
“ 春の風 冬の風を 追い散らし”