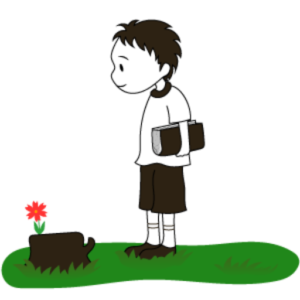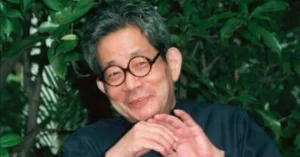先日、YouTubeをだらだら見ていたら、青汁王子さんこと三崎さんが「最速で一億円を稼ぐにはどうすればいい?」という視聴者からの質問に答える動画をやっていた。
短い動画なので、すぐ見終えられるが、簡単に言ってしまえば、
アフィリエイトをやり →元手を貯めて会社を作り → アフィリエイトの経験を生かして会社の商品を売る → 儲けが出た時点で事業を丸ごと売却する → お金持ちという手法である。
これはまさに、三崎さんが、実際に億の額を稼ぐために実際に辿った道筋でもあるらしい。
三崎さんは動画の中で、「こんなわかりやすい手法なのに、みんなどうしてやらないのか不思議だ、少し勇気を出せば誰に億万長者になれるのに」と言っていた。
確かにその通りだと思う。ただ問題は何の商品、サービスを売るのかだろう。いくら稼げるからと言っても、自分が欲しくもないものを売りたくない。それがどうにもひっかかる。やはり、どこか正しくない気がしてしまう。
このハードルが、結局のところ高いのだと思う。
多くの人も、それは確かに儲かるかもしれないけれど、飢え死にするほどにお金に困っていない限り、そんなことをしてまで儲けたくないなあと思うのが心情だろう。
アフィリエイトとは、格好良くローマ字で言い換えているが、つまりは『広告』である。
そして、三崎さんが他の動画でも言及していたように(意外に彼の動画を見ているかも)、広告を知り尽くしたものが今の市場経済を制する。
広告業界最王手の、電通さんがあれだけ力を持てるのも道理である(余談だが、村上春樹著『羊を巡る冒険』の背景でもある)。
そして、これを自分のこととして当てはめると、小説家も自分の文章を売るという意味では、売文家であり、作品が商品とも言える。
『ベストセラー』、『何万部売り上げ』という言葉があるように、出版業界も当然ながら市場経済にどっぷり浸かっているのだが、どこかで小説家というか芸術家は清貧を尊しを旨とするところがあって、自分の作品はそんじゃそこらの商品ではなく、お金という価値から離れたもの、別の価値があるものと思いたがる。
しかし、実際そう思ってはいても、市場に出した時、やはりより多く売れてほしい、お金を稼いで欲しい、あわよくば成功して、プロとして専業で生きていきたいとつい夢見てしまう。
はたして自分の作品を趣味レベルにとどめるのか、自分の作品をいち商品として、シビア市場経済にどうやって投げ込むのかを一度は真剣に向き合ってみないことには、やはり専業のプロにはなれないような気もする。
ちなみに、小説界では経済原理、市場原理、広告に精通してうまく体現できたのが、小説では村上龍さん、出版社では幻冬舎だと思う。
多くの小説家希望者が、稼げるがどうかの不安にかられて、ついネットなどで検索して、
『日本では専業の作家など10人もいない』。
『出版不況は今後も進む』。
『勤めは絶対に辞めない』等の情報を、あたかも己を説得するための意見とのように信じて、
だから「やっぱり小説家では食べて行かれない、趣味にしよう、諦めよう」という安易な結論を出すよりも、だったらどうにかしようか、から始まるのが健全な姿勢だとは思う。
言い換えれば、この先「書くこと」で生きていこうと覚悟するなら、書くことで、何らかの生活収入を得られるようにもっていくのが、ベストのような気がする。
確かに、勤めをやめずに、生活費を稼ぐためのサラリーマンや公務員をやりながら、小説を書き続けるというのは、堅実で賢明な判断に聞こえるが、そこには夢も希望の欠片もない。
とにかく勤めたくなくて、好きなように生きたいから小説家という選ぼうと思っているのに、そのために一生勤めなくてはならないという矛盾に、早かれ遅かれいつかはぶつかってしまう。それに、かつて植木等が歌っていた社会状況とは違い、もサラリーマンも気楽な商売ではない。
本気で言い作品を作りたいとと思うなら、「書くこと」をもっとダイレクトに金に換える手段にしてもいいと思う。このNoteの運営さんもその意図があるのを感じる。
かつて、文藝春秋社を創立した菊池寛も、スポンサーである広告主を探すのに本当に苦労したらしい。
これは、個人でも言えることで、個人としてスポンサーを集めることは芸術家にとって必要な手腕のような気がする。ミケランジェロだろうと、ダビンチだろうと、大金持ちのスポンサーがいたからこそ、あれだけの作品を作れた。
話は戻るが、この三崎さんの手法は、実は古くて新しい手法でもあり、我々ひよわな小説家にも、何か参考にできる部分がある気がする。村上春樹流に言えば「雪かき仕事」として。
もちろん、筆が荒れない範囲でだが。
“時間とお金“。
いい作品を作るための大前提。この二つを得るために、恥も外聞も捨てる瞬間が芸術家を志すために必要かもしれない。
と、言いながらもどこかで、広告というものにどこか浅ましさ感じてしまうのだけれど。
ではまた