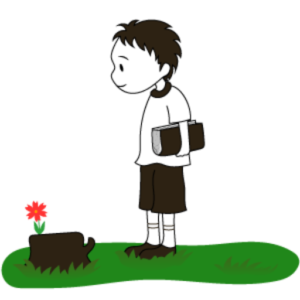円空の仏像が好きです。
身近に置いておきたくて、ヤフオクとかで出品されていないかよくチェックしています。きれいな模造品もありますが、あの荒いと言ってもいいぐらいの、素朴な味わいが消えてしまっています。
というわけで、ゴールデンウイーク、ずっと行きたかった円空の終焉(入定)の地となった関市を訪れました。
実は、近郊に住んでいながら、関市って一度もきちんと訪れたことがありませんでした(通過したことは何度もある)。近くて遠い町、刃物の町といったイメージを抱いていました。
円空とは、江戸時代初期の僧侶であり、諸国を巡りながら、苦しい暮らしを強いられていた民衆のために、生涯で12万の仏像を作ることを発願し、実際に作り終えた人です。
円空の仏像って、ネットでごらんになればわかるとおり、町の通りの片隅に座ってらっしゃるお地蔵さんと同じく、その「微笑」がすばらしく、魅力的なのです。
当時、特にぎりぎりの生活をしていた農民の人たちは、ふらっと訪れて残していった、彼の仏像の微笑みに感激し、心からの「救い」を願ったのだと思います。
残っている仏像の一部が、部分的に変色したり、すりへっていたりしているのは、大伽藍に収まってる観音像のように、畏れ多く仰ぎ見る対象ではなく、それこそすがるような思いで、仏像自体をぎゅっとにぎりしめ、ときには抱きしめたりしていたせいでしょう。
今でも、全国に5千体以上の仏像が残っているのは、それぐらい多くの人が心から大切にしてきたからこそです。
円空の生き方は、どこか良寛にも似て、種田山頭火にも似て、和歌や俳句を詠う代わりに、円空は仏像を彫ったのでしょう。
円空は廃寺になっていた関市の弥勒寺という寺を再興させ、そこで晩年を過ごします。そして病を経て、長良川湖畔で入定します。
そのとき、近隣の多くの住人たちに心から惜しまれながら、死んでいったと言われています。そのときは、おそらく円空が自ら彫った仏像のような微笑みを浮かべていたことでしょう。
私は仏教徒ではないですが、僧侶が好きです。というより彼らが作る芸術(思い?)が好きです。短歌や俳句、円空のような仏像、水墨画、お茶。それらは、彼らがそれぞれ抱いていた、祈りの言葉そのものと言っていいからです。
それらは、経文に書かれた難しい言葉よりも多くの人の心を救ってきたに違いありません。
旅の話に戻りますが、円空の美術館を観て、弥勒寺の跡地を巡り、雄大な長良川の川べりを歩いている内に、ふと、宮沢賢治のことを思い出しました。花巻に似た土地の雰囲気を含めて、ああ、何だか似てるなと。そして、円空がこの地を終焉の地に選んだ理由もわかりました。いいところだと。
宮沢賢治は僧侶ではありませんでしたが、熱心な法華経系の信者でした。世界の人々全員が救われない限り、自分も救われない。そういった途方もない理想を抱き、たくさんの童話を残し、羅須地人協会の活動を行いました。
彼が産みだした童話も、彼の祈りの言葉の一つであり、円空の仏像のような微笑みを童話の中に感じます。だからこそ、彼の童話は、今でも読み継がれているのでしょう。
人って実はこうなんだよ。人が抱える闇ってこんなもんだと晒していく文学もありですが、私としては、円空や宮沢賢治が願った「祈り」の気持ちを、創作のベースにしたい。そして、常に忘れないようにしたい。と苔むした階段の先にあった円空のお墓に誓ったのでした。
そのためにも、円空の仏像を何とか一体手に入れたいなあ。どこかでお値打ちに売ってないかな。
ではまた