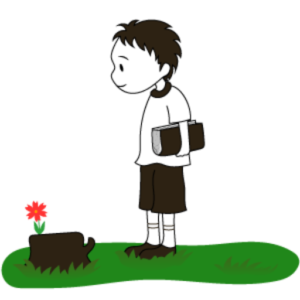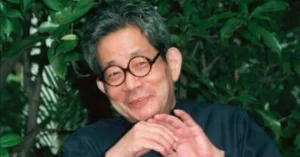最近、芸術新潮10月号で「お茶」の特集を読んでから、利休のブームがやってきました。実は、このブームは初めてではなく三度目です。
一度目は、数十年前に、母方の祖父が亡くなったとき、遺産分け代わりに、茶道具一式をもらった時でした。
祖父はどうやら、正業である陶器製造の傍らで、華道の中の古流(?)という流派の師匠をやっていたらしく、その稼業も花を生けるために相応しい陶器が見つからないので、自分で作り始めのがきっかけでした。当然、その関連としてお茶を嗜んでいて、茶道具が残ったというわけです。
両親は華道も、茶道もそれほど興味がなく、その古ぼけた茶道具一式は、なぜか私に譲られました。まだ、中学生だったので、それはただの木でできた得体のしれない道具でしかなく、どう触っていいのかすらわかりませんでした。
しかし、この古い茶道具はなぜか、心に訴えるものがあって、時々押し入れから出してきては、ぼーっと眺めたりしていたのですが、たまたまテレビで、利休の映画を観たせいもあって、抹茶ではなく煎茶を入れて飲んだりするようになりました(変な中学生ですね)。
そのとき、両親にお茶を習いたいと言ったのですが、即座に却下されました。母親ぐらいは喜んでもらえると思ったのですが、まったくの拒否反応でした(たぶん無理矢理習わされて嫌いだった)。
時代的にも、お茶は、男の習い事ではなく、花嫁修業とか、いいところのお嬢様がやるものだという風潮が強くて(今も?)、言い出すこと自体がかなりのハードルが高いものだったのも確かです。
私としても、ごねてまでやるパワーもなく、代わりにギター教室に行くことになったのですが、その顛末の話は別の日に譲るとして、それっきり茶道具一式は、押し入れにしまい込まれることになりました。
それから、再び月日が流れ、家族で引っ越すことになり、久しぶりに茶道具を表に出すことになりました。
すると、驚いたことにほとんどが虫に食われて、穴があいているどころか、ほぼ原形をとどめなくなるほどに朽ちてしまい、茶筅の先だけが虫たちもおいしくなかったのか、残っているという惨状。あとはひたすら虫のふんだけ・・・。
そのまま、茶道具一式はごみ箱行きになってしまいました。
そのときに母親が、「そういえば、あんたを見ていて、お父さん(祖父)は、常々孫の中(十五人ぐらいいる)で、おれに一番に似ているかもしれん」と言っていたことを、突然思い出し、だから私に茶道具を上げたと言い出したのです。
それを聞いて、なんでもっと早く言ってくれなかったと思いながら、せっかく遺してくれた茶道具一式をゴミにしてしまったという罪悪感が襲ってきました。
「おじいちゃんごめん」。と当時大学生だった私は、心から反省して、再びお茶関係の本を読みだしたのです。
岡倉天心の「茶の本」を始め、利休の伝記、映画、などなど。しかし、なぜか、その時はすぐにブームは終わり、習いたいとも思いませんでしたが。
そして、今回が三回目。時代も変わり、再びお茶を習いたいと思っていろいろ調べたんですが、流派もたくさんあって、どれがいいのかわからない。それにやっぱり敷居が高い・・・。(ちなみに、黒木華さんと、樹木希林さんが出演されていた「日日是好日」はとってもいい映画です)。
というわけで、結局は、自己流でやろうかなということに落ち着きました。「利休入門」木村宗慎著さんの本を読んだのも大きいです。
昔の茶道はもっと自由で、おおらかだったとありました。利休が今の茶道の世界を見たらきっと驚くと。
結局、茶の本質を掴み、その精神さえ表すことができれば、茶器とか、掛け軸とか、茶室などという形はどうだっていいんだという、いつもの勝手な独断に至りました。
「茶道とは、主人がお客を心からもてなしながら、俗(政治、経済)から離れた物事について談笑すること。道具はあくまでその手段にすぎない」と言い切ったら怒られるかな。
ではまた