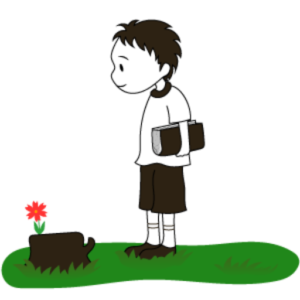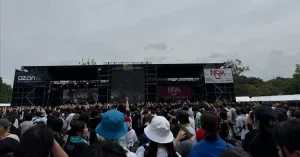晴れ
寒い 寒くて体調が悪いと、嫌なことばかり考えてしまう。
正直言って、ずっと、相田みつをさん(以下敬称略)の作品があまり好きではなかった。
初めての出会いは、かつて働いてた職場のカレンダーを、ある同僚の女性が、勝手に相田みつカレンダーに変えたことだった。壁に貼り終えた彼女は、「いいでしょう、いいでしょう」とひとりご満悦だった。
ちなみに、彼女はかなりの相田みつを信奉者のようで、卓上カレンダーはおろか、鞄にも「だって人間だもの」と入ったキーホルダーをいつもぶら下げていた。
私としては、その行動にまず、「えっ?」と思ったのと同時に、どうしても毎日、相田みつをの詩が目に入ってくる。
「しあわせはいつも自分が決める」、「やれなかった やらなかった どっちかな」。「他人のものさし 自分のものさし それぞれ寸法がちがうんだな」等々。
しかし、当時はかなりとんがっていた自分は、正直言って受け付けなかった。詩と言うより、「わかるけど、ただの処世訓でしょ」と密かに思っていた。月が改まり、新しい言葉が目に入ってくるたびに、ぞっとしていた。
当然ながら、同僚の熱い信奉者には、そんなことは言えず、「いい言葉ですね」、「生きる勇気が出ます」と、おべんちゃらを言っていた。その同僚はいつも満面の笑顔でうなずいてくれた。
しかし、あれから数十年たち、相田みつをブームも去り(一時期、入る居酒屋、居酒屋のトイレには申し合わせたように、相田みつをの言葉が張ってあった)。
ふと、相田みつをさんの人生が書かれた本を読んだとき、なるほどなと思った。相田みつをは、自分のことを「書家ではなくて坊主だ」と常々言っていたというのがわかった。そうか、それで急に腑に落ちた。あれは、禅を学んだいち居士として言葉だったのだと。
別に誰かを説教しようとか、人生訓を述べたかったわけではなく、禅の精神をわかりやすい言葉として表現したかったのだ。そう思ったとたん、これまでの言葉が、まったく違う意味を帯びて聞こえるようになった。
相田みつをって、案外奥が深いぞ。
たぶん彼は、考えに考えて一周回って、ああいう言葉を発するようになったのだと急に理解できた。街角でよく見かける、名言イラスト売りとは格が違うのも当然だと。やはり売れた理由には意味がある。
あわてて、未公開のメモ書きや、過去の作品をあさってみた。すると、メジャーになってない言葉の数々が、かなりいいことがわかった。
そこには、一見穏やかだが、かなり厳しい言葉が並んでいた。名言とされる、まるで人をあやすような言葉はあくまで氷山の一角であって、その下には詩的直感と禅の精神が絡み合った、深くて暗い言葉の深海が存在した。
相田みつをが世に出たのは60歳過ぎてからだった。苦労したからこそ、あの水の上澄みのような言葉を、「敢えて」吐けるようになったのだ。
そこには、書家としてよりも、坊主(居士)として、この世の迷える凡夫を救おうとする意識があったような気がする。
やはり、流行というのは表面だけで捉えてはダメだあと、今回のことで本当に痛感した。
相田みつをさん、ずっと嫌っていてごめんなさい。少し好きになりました。
ではまた