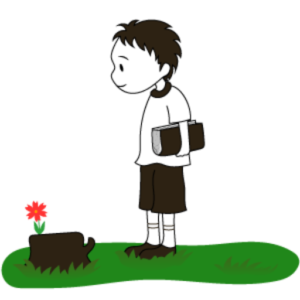晴れ
穏やかな冬晴れ 実はこういった日こそ一年の中で、一番いい季節かもしれない。
吉本隆明全集6巻「晶文社」を読み進める。その中で「詩とはなにか」を真剣に読む。
その中で、「詩とはなにか。それは、現実社会で口に出せば全世界を凍らせるかもしれないほんとうのことを、書くという行為で口に出すこと」とある。
さらに萩原朔太郎「詩の原理」を引用して、「詩が本質する精神は、この感情によって訴えられたる、現在しないものへの憧憬である」。
つまりは、簡単に言ってしまえば、詩とか歌は、ワァとか、ウオーーという、言葉以前の肉声である「叫び」が元になっているということである。それを誠実に言語化すると、詩や歌となり、場合によっては、「世界を凍らせる」言葉になるだけの違いだと。
「人は、誰しも詩人であり。人間の現存在はその根底において、「詩人的」である」と言ったのは、哲学者であるハイデッガーだが、詩人とは別に特別な人をいうわけでなく、叫びを上げる人は、みな基本的に詩人になれるという意味だろう。
それを上手く言語が出来る人が、世に言う「詩人」と呼ばれることになる。きっと、松尾芭蕉は、古池に蛙が飛び込む水音を聞いて、心の中で最初に、ウォーと叫んでいたのだと思う。
続けて、なんて趣があるんだ。これを何とか言語がしようと思ったに違いない。
それが、たまたま俳句となっただけで、西洋に生まれていたら、もっと長い詩を書いていたかもしれない。
この、「ウォー」は、人によっては涙かもしれない、拳を握りしめることかもしれない。そして私のようにため息かもしれない。
吉本さんは言う、「詩が書き終わったとき、散文である事実をうまく指示したとき、比較にならない充実感または空虚感を持つ」そして、この充実感や放出感は、「どこか憑いた感じに似ている、自己が自己に憑いた感じである」と。
身も蓋もない言い方だけど、「すっきりする」のだ。それが人に読まれる価値があるか、芸術かどうかは関係ない。良寛や吉野秀雄さんを初め、多くの歌詠みが、プロの作品より、名も知れぬ人たちの歌集、「万葉集」にひかれたように、素直に詠うことが何よりも大切なのかもしれない。
さあ、叫びたい人は、その叫びを言葉にしよう。TwitterでもNoteでもいいから。
なんて・・・柄ではないアジテート。
とりあえず、自分のため息はへぼ俳句に・・・。
初詣の 人混みまみれて 淋しさまさり