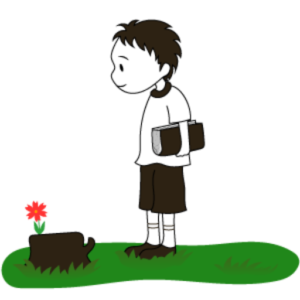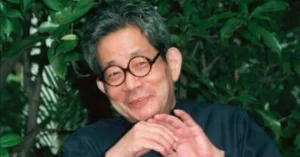このところ、朝方に瞑想を行うのが習慣になっています。
瞑想をしていると言うと、少し前まではオカルトっぽいか、宗教的なイメージが強かったと思いますが、近頃は、瞑想を健康法の一つとして扱われるようになり、かなり一般化してきました。
それでも人に話すと、相手によっては怪訝な表情をされることもありますが、やっている人も多くなってきて、共感されることも多々あります。
しかし、自分の瞑想のやり方は、あくまで自己流です。座禅の本や瞑想の入門本などをちらっと読んで始めたものです。
本格的に、ヨガや禅などをやっている人からすれば、まったく違っているかもしれませせんので、それこそ途中で?と思われた方はそちらの本を読んでください。
自分にとっての瞑想の定義は、怒られるかもしれませんが、簡単に言って「思考を切断すること」だと思っています。
つまり、人は生きている限り、いろいろな想念が浮んでくるのを止められません。当たり前ですが、常に何か考えてます。若しくは感じています。生老病死、仕事のことや家庭のこと、人によってはこの国の未来、世界の平和まで、そこまで大げさでなくても、やりかけのゲームや、ドラマの続き、野球の結果など、ぼーっとしていても、実はいつでも何らかの思念を必ず浮かべているものです。
つまり起きている間は、脳(果たして脳が、本当にすべてを考えているかどうかという話はまた別の機会に)がフル回転しているというわけです。
逆に、強いストレスに見舞われ、ずっと一つの想念に頭が支配されて、オーバーフローになっている場合もあります。それ以外のことは考えられない。うつ状態というのは、そういう状況をさしているのでしょう。
その思念を断ち切る訓練をすることで、何も考えない時間、脳を休めることができるのだと思ってします。その手段として、一番有用なのが、私にとっての瞑想だというわけです。
おそらく、もう一段高レベルの瞑想ならば、完全に自分を忘れる。つまり、それにまつわって起こる様々な煩悩からも自由になれるかもしれません。
生老病死に対する恐怖から自由になることが、悟りと言われていることならば、瞑想している間は、少なくとも悟っているかもしれません。
ただし、お釈迦様のように、完全に悟ってしまったよう偉人ではないので、あくまで瞑想している間(それもつかの間)だけですが。
ただ、瞑想を長らく続けている方にはよくわかると思いますが、その境地は中々筆舌で言い難いもので、とても澄み切った、それと同時に全能感に包まれた独特の感覚があります。達磨大師が、ひたすら座禅を組んでいた理由がよくわかります。
ただし、問題はこの瞑想をうまくやるのが、簡単そうで本当に難しいことです。私も長年やっていますが、うまくいくのは十日に一回あるかないかです。
いつもの手順に従って瞑想に入るのですが、すぐ日常の悩み事や、過去の出来事、後悔したこと、小さな悩みに振り回されるだけで終わってしまいます。それでも何とか、次から次へと上ってくる想念を叩き潰す(イメージはもぐら叩き)ことを試みます。
しかし、本当にまれに「己」というものを消すことができ、天のようなもの(天が何を指すかはいろいろな考え方がありますが)と一体になれたような瞬間があります。それを求めてやるのですが、恐らく、それが夏目漱石が言う「則天去私」の境地なのでしょう。
夏目漱石の小説にも、何回か悩み疲れた主人公が禅寺に行く場面があります。しかし、だいたいが失敗に終わって下界に戻ってきてしまいます。
最後の最後まで煩悩から逃れ切れない。これらの主人公と一緒にしてはだめですが、あの大文豪ですら完全な瞑想はマスターしきれなかったのかもしれません。それぐらい瞑想は難しいものだと思っています。
これは、技術的な問題になりますが、曼荼羅の絵や梵の文字を見つめ続けたり、薄目を開けながらある音に集中したり、高い山に登って空気のいいところでやったりと、まずは集中するためにいろいろな工夫が試みられたりしているのもそのせいでしょう。
ただ、時々、ただすべては幻想で、自分はやった気になって満足しているだけかもしれないと思う時もあります。テレビ番組で、わざわざヨガマットを担いでいって、山のてっぺんまでに登って、ヨガをやった後に瞑想している人を見たときなど、本当に瞑想ができているのかまるで自分を見ているようで心配になります。言い方は悪いですが「こういうところでヨガをやっている自分が好きな」ので終わっていやしないかと。
かといって、激しい修行(滝に打たれたり、護摩行をしたり)もお勧めしません。別にそこまで頑張らなくても、瞑想なんてものは、座禅を組んだり、絶対的な静寂の中でやらなくても、飛行機の中やスタバの中でも、下手したら寝転がりながらでも、やれるものだと思っています(飛行機の中がお勧め)。
瞑想をしていると、数十分があっという間に過ぎてしまいます(そこまで行けるのは数年に一回ぐらいですが)。その結果、とにかく頭がすっきりします。頭の回転がよくなった(気がします)。お酒とは真逆のトリップ感をイメージしてもらうといいかもしれません。
夏目漱石が天と一体となって、我を忘れえた忘我感を「則天去私」と名付けたように、これを自分風になぞらえれば、自我が天と一体になった「則天唯私」ってところかもしれません。
だからもし、ここまで読まれて、いろいろな悩み事や考え事で頭がいっぱいになってしまって、頭がフリーズしそうになっている方は、瞑想を試してみられるのも一興だと思います。
ただし、瞑想の世界に入ってしまい、うまく戻って来られなくなる人がいるらしいので、まずは何かガイダンスのようなものを読んで始めるのをおすすめしますが。
座禅でいう「渇」というのは、眠っているのを起こしたり、怠けているのを戒めるためではなく、喝という物理的な力で、思考を飛ばすという意味だと知った仲村でした。
ではまた